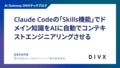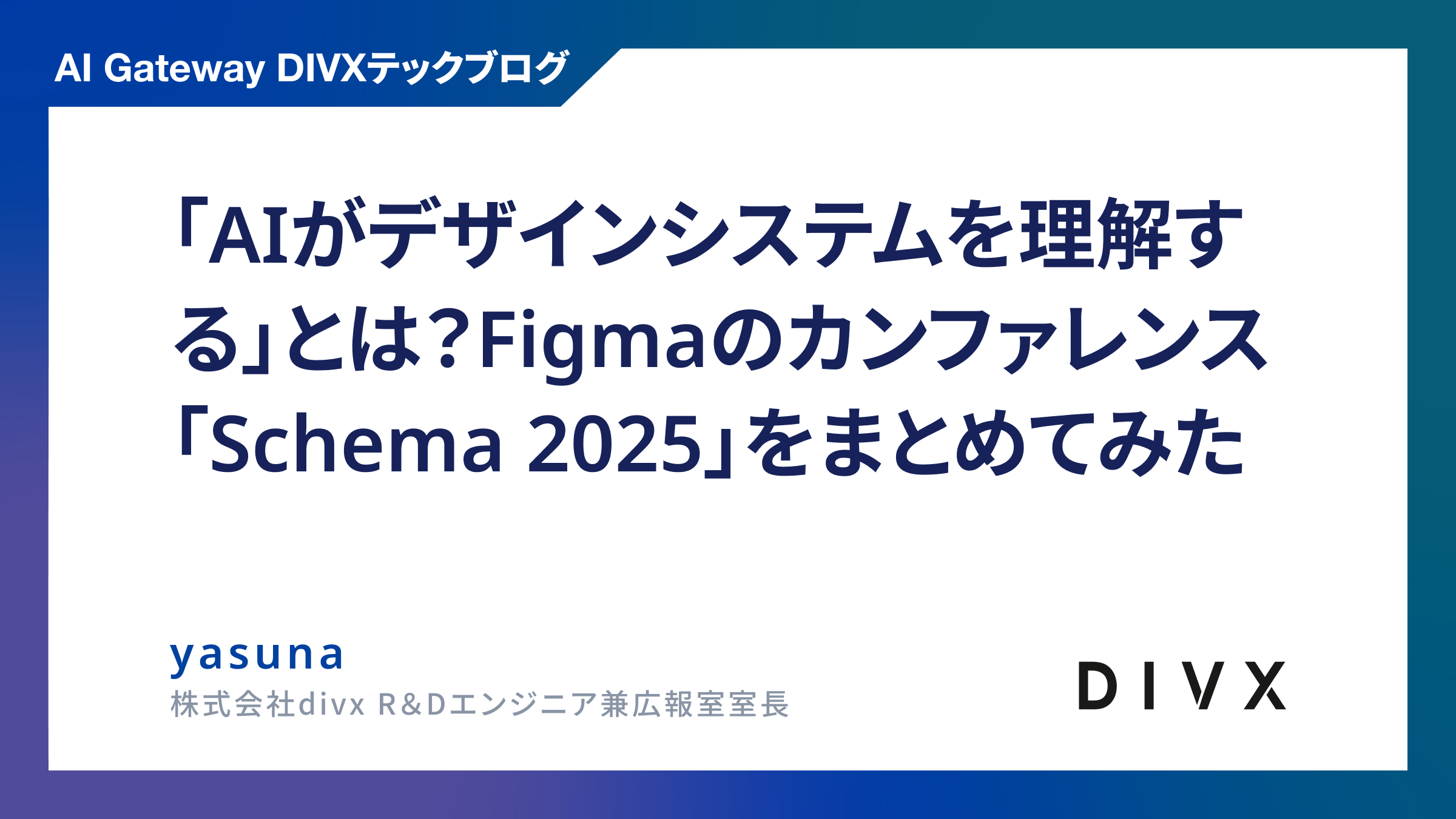
「AIがデザインシステムを理解する」とは?Figmaのカンファレンス「Schema 2025」をまとめてみた
はじめに
こんにちは、DIVX R&Dエンジニア兼広報室室長のyasunaです。
2025年10月28日、Figmaのデザインシステムに関するカンファレンス「Schema 2025」が開催されました。生成AIが私たちの開発プロセスに急速に入り込んできてから、デザインとエンジニアリングの境界はこれまで以上に曖昧になってきていると感じます。
今回の発表は、まさにその「境界」でいかにして品質や一貫性を保ち、むしろAIをどう活用してプロセスを加速させるか、というFigmaの強い意志が示された内容でした。この記事では、発表された内容を振り返りながら整理します。
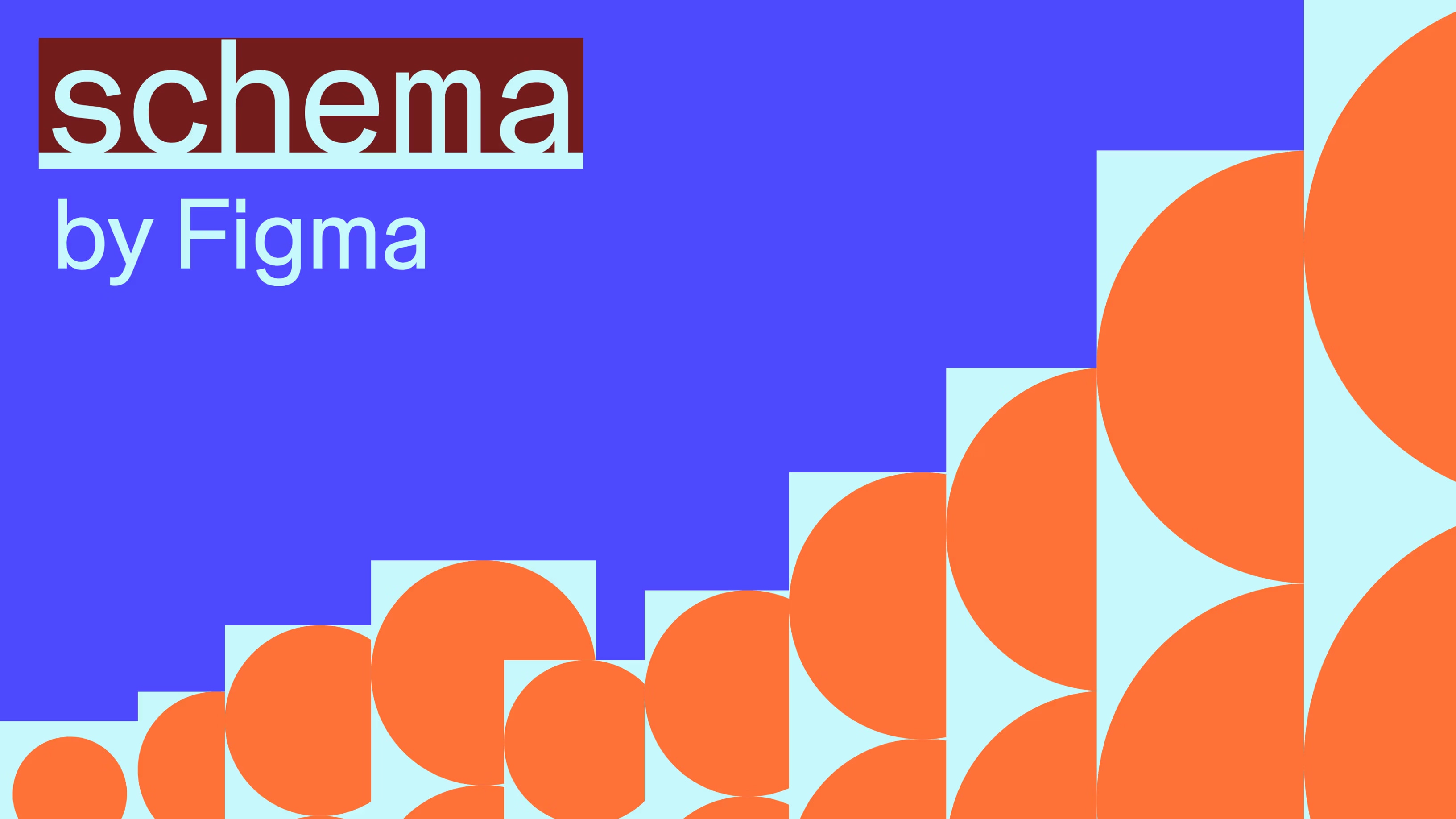
https://www.figma.com/blog/schema-2025-design-systems-recap/
この記事を読んで分かること
この記事では、Schema 2025で発表された主なアップデート内容を要約し、それらがAIを活用する現代の開発プロセスにどのような影響を与えそうか考察していきます。
背景
今回の発表の基調にあったのは、AIツールがプロダクト開発に参加することが当たり前になる中で、品質やブランドの「らしさ」といった「テイスト」の重要性が増している、という認識です。
デザインシステムは、これまで主にデザイナーと開発者の間での「一貫性」を保つための静的な標準として機能してきました。しかしFigmaは、これからのデザインシステムは、AIがデザインとコードの両方を理解するための「翻訳者」としての役割を担う必要があると述べています。
今回のアップデートは、デザインシステムを静的な標準から、プロダクトチームがその上で構築できる「生きたシステム」へと進化させるためのものだと感じました。
発表されたこと
まず、デザインシステムの管理をより柔軟で拡張するための機能が発表されました。
「Extended collections」は、例えば複数のブランドや製品を持つ企業が、共通の親システムを維持しつつ、各々で必要な部分(例えば色)だけを拡張(上書き)して、独自のテーマを管理できる仕組みです。
「Slots」機能も、コンポーネントの柔軟性を高める上で大きな一歩だと感じました。これまではコンポーネントの構造を一部変更したい場合、インスタンスを「デタッチ(切り離し)」する必要があり、システムとの接続が切れてしまうことが課題でした。Slotsによって、システムとの接続を保ったまま、指定された箇所に新しいレイヤーを追加するといったカスタマイズが可能になります。
AIの活用も具体的に進んでいます。「Check designs」は、私たちがデザインした要素が、意図したデザインシステム上の変数(トークン)を使っているかをAIがチェックし、修正を提案してくれるリンター機能です。これにより、開発者に渡す前の「意図しないズレ」を減らすことができそうです。
また、根本的なパフォーマンス改善も行われたようです。変数やモードの切り替えといった操作が30〜60%高速化されたとのことで、これは複雑なシステムを扱う上での日々のストレス軽減に直結する、地味ですが非常に重要なアップデートです。
開発者にとって最も大きな影響がありそうなのは、「コードとの連携」の強化です。
「Code Connect UI」は、FigmaとGitHubリポジトリを直接つなぎ、AIがコンポーネントと実際のコードファイルとのマッピングを助けてくれる機能です。これにより、デザインシステムチームはコーディング不要で、デザインとコードの連携を迅速に確立できるようになります。
https://developers.figma.com/docs/code-connect/code-connect-ui-setup/
そして「Figma MCP server」がベータ版を終え、一般利用可能になりました。これは、AIコーディングエージェントが、私たちのデザインシステムやFigma上の文脈を理解し、それに準拠したコードを書くための基盤となるものです。
https://www.figma.com/blog/introducing-figma-mcp-server/
さらに、「Figma Make」というプロンプトからアプリを生成するツール内でも、Figmaライブラリから生成した「Make kits」や、既存のnpmパッケージをインポートし、デザインシステムに基づいた生成ができるようになるようです。
https://www.figma.com/blog/introducing-figma-make/
考察:デザインとコードの「文脈」をAIに伝える
今回の発表全体を通して私が強く感じたのは、Figmaがデザインシステムを「デザインの意図」と「コードベースの現実」という、両方の文脈を持つ「ハブ」として再定義しようとしていることです。
私たちが日々AIを活用して開発効率を上げようと試みる中で、最も大きな課題の一つは、AIがいかにして「私たちのチームのルール(デザインシステムやコーディング規約)」を正確に理解し、それに準拠してくれるか、という点にあります。
Code ConnectやMCPサーバーの強化は、まさにこの課題に対するFigmaの具体的な回答だと感じました。AIがデザインシステムという「共通言語」を深く理解し、デザイナーがFigma上で定義した「意図」を、開発者が使う「コード」へと、より正確に変換してくれるようになると感じました。
まとめ
Schema 2025の発表は、デザインシステムが単なるコンポーネント管理ツールから、AI時代のプロダクト開発における「品質と文脈の中心」へと進化していることを明確に示していました。
Extended collectionsやSlotsによる設計の柔軟性の向上、そしてCode ConnectやMCPによるコードとの強固な連携。これらが組み合わさることで、AIを含めたチーム全体が、より高い品質を維持しながら迅速に開発を進められるようになるのではと思います。
デザインと開発の境界線は、AIによってさらにシームレスになっていくのだと改めて感じました。私たちもこの新しい流れをうまく掴み、日々の開発に活かしていきたいですね。
ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。